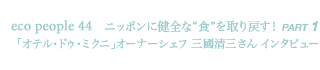つまりこの感覚は、僕たちが動物として、生まれながらに備えている自衛本能として反応する味なんだ。この味を出すと子供たちは間違いなく、“ペッ”と吐き出す(笑)。ところがこの“苦み”も、大人になると、自分の人生の経験を反映し、妙に惹かれる味として認知される。ほろ苦い経験と重ね合わせて評価する苦みの味わい、奥が深いよね。そして5つ目の味、“うま味”。“うま味”を奏でる成分には3つの代表格が上げられる。まずは昆布に含まれるグルタミン酸、次にイノシン酸、鰹節にたくさん含まれている成分。さらに、干し椎茸などのキノコ類に含まれているグアニル酸だ。つまり、日本食の味のベースとも言える昆布だし、鰹節、干し椎茸には、この“うま味”がぎゅっと詰まっているんだ。日本人の食で古くから大切にされてきた“ダシ”には、この“うま味”の系譜が脈々と流れている。もちろん、この“うま味”の要素となるグルタミン酸やイノシン酸は欧米の食品、チーズやトマトにも含まれているんだけれど、これらの食品には酸味や甘み、それに濃厚な味わいが持つ“油味”があるので、日本の伝統的な食文化のように、“うま味”を強く感じるのはちょっとばかり難しいんだ。
編集部:でも何故、この5つの味覚の識別を“食育レッスン”のポイントに位置づけていらっしゃるんですか?
三國:ちょっと横道に逸れるかもしれないけれど、ウミガメの孵化シーンを思い出してくれないか? 生まれたてのカメの赤ちゃんたちは卵から孵り、目も見えないのに、迷う事なく海へ向かってゆくよね。人間の赤ちゃんも同じで、生まれた途端にお母さんのお乳を求めて一生懸命“吸う”動作をする。胎盤から離され、これから自分で生きて行くために“食べたい”という意思表示をして、なんとかお乳にありつこうとする。つまり、この瞬間から“食”は人間にとって最も重要な生命維持行為として、外界と繋がる“入り口”になる。
舌の上には食べ物の味を感じる味蕾(みらい)という器官があることは知っているだろう? 無数の味蕾は、口から入る食べ物をその上に受け入れ、それぞれの味覚を脳に伝える働きをする。成人で約10,000個(*1)と言われるこの味蕾の中にある味細胞というものが味覚を受容して、脳に刺激として伝えられるんだ。そして脳、つまりその人間はこの情報をキャッチしてさまざまな感情を豊かにしていく。一方、食べ物はその後、食道、胃を経て消化され、肉体を養ってゆく。僕はね、“味をしっかり感じ、美味しく食べる”ということにこそ人間の心身を育てる原点があると考えているんだ。
編集部:なんだか大きな関連性が見えてきたような気がしてきました。“食べる”という本能にこそ、様々な感覚を刺激し、かつ肉体を育てる要素があるというコトですね?
三國:食べ物をしっかり味わってこそ、血となり、肉となる。僕は“しっかり噛み、味わって食べること”は脳を活性化して、五感を磨くと思っている。“視覚”、“聴覚”、“触覚、“臭覚”そして“味覚”、この一連の感覚にもっとも正直で敏感なのは8歳から12歳頃、異性よりも自分自身に深い関心を持っている年代の子供たちだ。だからこの年齢層に重点をおいて、「食育レッスン」を開催しているんだ。
編集部:異性を意識しだすと、味覚は衰えてしまうのですか?
そういう意味じゃない。誰かを好きになることで自分の感覚、判断が二の次になるという意味だ。彼や彼女が美味しそうにしてくれれば、それで自分は満足という判断が生まれてくる。これはこれで世の中を平和に保つ上で必要な判断だし、誰かと共通の幸せを分かち合うための最初の約束事かもしれない! 彼女や彼の反応に歩み寄れないというのも、ちょっと問題だよ。(笑)