- エコビーイングは未来の世代に健康な地球を伝える環境サイトです。
- エコビーイングとは?


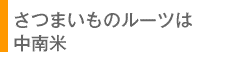 |
さつまいもの原産地は中南米の熱帯アメリカ。最古の考古学的資料によると、そのルーツはペルー海岸のチルカ谷の遺跡から出土した炭化したさつまいもの根で、紀元前8000年から10000年前のものと推定され、紀元前3000年頃には熱帯アメリカで一般に食べられていたのではないかと考えられています。 伝来のルートはいくつかあるようですが、記録によると、16世紀にインド、マレー、インドネシア、フィリピンヘと伝わり、1584年には中国の福建省に伝えられたとされています。 日本に渡ってきたのは約400年前。宮古島に入ってきたのが最初で、琉球(沖縄)から薩摩(鹿児島)を経て、日本全国に普及していきました。さつまいもは干ばつや土壌条件に強く、荒れ地のやせた土地で簡単に栽培できるため、飢饉に備える格好の作物として、 今では世界中に広がり、熱帯、亜熱帯はもとより温帯地方でも栽培されています。 |
|
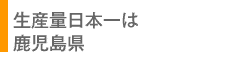 |
さつまいもは、ヒルガオ科サツマイモ属の植物。2002年のデータを見ると、さつまいもの作付面積は世界全体で約977万ha、生産量は約1億4000万トン、じゃがいもの約半分となっています。アジアが全世界生産の90%を占め、特に中国は世界の84%と群を抜いています。ウガンダ、ナイジェリア、インドネシア、ベトナム、ルワンダ、インド、日本などがこれに次ぐ主産国です。 日本は昭和30年の700万トンがピークでしたが、しだいに食生活が豊かになり、多様化とともに生産は大きく減少。現在は約4万ha、約100万トンとなっています。そかしその用途は青果用をはじめ、菓子などの加工食品用、焼酎醸造用、でん粉原料用と幅広く、南九州や関東の畑作地域において、地場産業の振興になくてはならない作物となっています。中でも鹿児島県では、年間約50万トンのさつまいもが生産され、これは全国生産量の約40%にあたり、種類も豊富です。鹿児島は名実ともに日本一のさつまいも王国となっています。 |
|
 |
世界的に見ても、さつまいもの主食利用は大きく減少しています。しかし日本では昭和50年前後を境に、少しずつではありますが1人当たりの消費量が増加の傾向です。その背景には現代人の高い健康意識が大きく関係していと考えられており、さつまいもの長い歴史の上に、医食同源にかなった新たな食文化が生まれているといえそうです。 |
|
 |
さつまいもは、でん粉を主成分にセルロース、ペクチンといった食物繊維が非常に多く含まれ、ミネラル類、各種ビタミン類など、様々な栄養素を豊富に含んだ高機能・低カロリー食品です。特にビタミンCはリンゴの10倍以上もあり、1本(約200g)で1日の必要量をほぼ摂ることができます。 さつまいものビタミンCは加熱調理しても壊れにく、細胞の結合を強化するコラーゲン生成を助ける機能があるため、美容にも打ってつけです。また、野菜の中でも多く含まれているビタミンEは、細胞の老化を遅らせ、みずみずしい肌を保つ働きがあるといわれています。たんぱく質と脂肪を補えば理想的な食事ができるため、準完全栄養食品として見直されています。 |
|
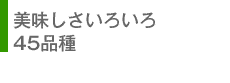 |
八百屋の店先に最も多く出回っているのは、ホクホクとした味わいと鮮やかな紅色が特徴の「ベニアズマ」です。平成14年の調査では、45品種の作付が報告されていますが、それ以外にも統計に入っていない地域在来的な品種が数多く栽培されているようです。 さつまいもは品種によって肉質や糖分の量が異なるため、その特徴に応じて使い分けることで、素材のもつ旨味を引き出すことができます。 甘みの強い「ベニアズマ」「紅小町」「高系14号」は天ぷらや、ふかして。アクの強い「紅赤」は、皮が容易に剥がれ蒸し時間が短く、繊維も少なく変色しないため、きんとんや煮物に向いています。肉質と食味が重要な焼きイモは「ベニアズマ」「農林1号」「紅小町」が適しています。 珍しいものでは、皮が白い「コガネセンガン」を焼きイモにしたり、肉色が濃い橙色の「ベニハヤト」はアイスクリームなどの製菓用に。また、ふかしても甘くならない「サツマヒカリ」は加工食品向けに使われます。また、紫芋品種の「パープルスイートロード」も近年人気を集めています。 |
|
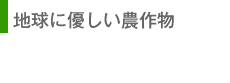 |
地下で成長するさつまいもは病虫害や風水害に強く、農薬をほとんど使わずに作れる数少ない農作物の一つです。農薬を使うのは、葉が病虫害に冒された時だけ。その場合も、地下にあるさつまいもには直接農薬がかかることがなく安全です。 また、肥沃な土地よりも荒れた土地を好むため、過剰な化学肥料を与える必要がなく、大型のプランターや肥料袋でも簡単に栽培することができます。家庭菜園で育て収穫したさつまいもを、自分で調理し味わってみるのも一興です。 |
|